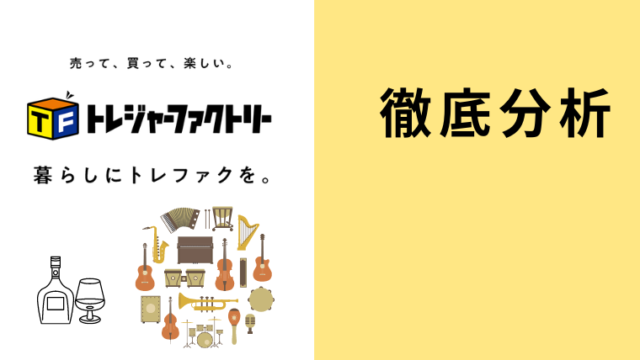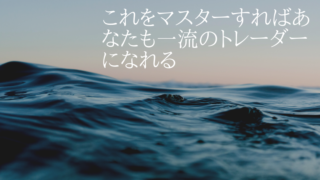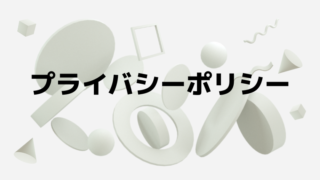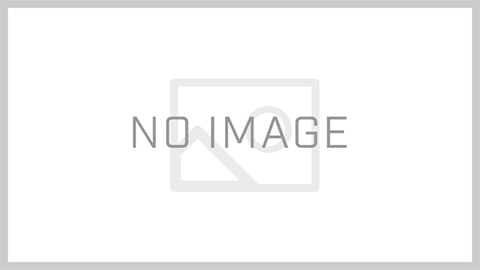歴史
SONYは1946年に井深大氏と盛田昭夫氏の2人で東京通信工業として出発しました。
1979年にウォークマンを発売。
90年代まで安定的な利益を上げていたSONYでしたが2000年代に入りIT革命に取り残されてしまうことになります。
そのため2000年代は不採算事業を切り離し、経営へのテコ入れが中心となっていました。
現在のSONYはエンターテイメント事業が中心になっている。
2013年のSONYは売り上げ構成の中心がHome Entertainment(家庭用娯楽)とMobile Communication&Products(携帯関連)でしたが、2019年になるとネットワークを使ったゲームやエンターテイメントなどのソフトウェア事業が収益の大きな柱になっていることがわかります。
SONYの事業の中心は8つあると考えてよいでしょう。
「Gme&Network Service」、「Semiconductors」、「Financial Services」といった事業に選択と集中をした。
Gameにおけるストリーミングゲームではマイクロソフトと組んだり、半導体におけるイメージセンサーではアップル、Huaweiなどのスマホへのセンサー提供などで高利益率を保持している。
そしてSONYはここ数年でLiabilities(負債)をかなり増やしてきました。2015年と比較すると約20%の増加です。
その理由の一つはSONYのFinancial Service部門であるソニー生命やソニー損保が好調で利用者への責任準備金等である非流動負債が増加したからと考えられます。
総資産における長期投資割合が56%を占めています。これは有価証券への投資が中心でたとえばSpotifyへの投資などが挙げられます。
過去数年間のSONYの売上推移をみると頭打ち状態になっていることがわかります。
その一方でOperating Profit(営業利益)は改善しています。Game&Network ServicesとMusicの営業利益が上昇しているためです。
21年3月期(2020年4月1日~2021年3月31日)
22年3月期(2021年4月1日~2022年3月31日)
23年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)
。
業績
| (百万円) | 売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 |
| 2017 | 7,603,250 | 73,289 | 288,702 | 0.96 | 3.80 | |
| 2018 | 8,543,980 | 490,794 | 734,860 | 5.74 | 8.60 | |
| 2019 | 8,665,687 | 916,271 | 894,235 | 10.57 | 10.32 | |
| 2020 | 8,259,885 | 582,191 | 845,459 | 7.05 | 10.24 | |
| 2021 | 8,999,360 | 1,171,776 | 971,865 | 13.02 | 10.80 | 21.2 |
| 2022 | 8,396,702 | 882,178 | 1,202,339 | 10.51 | 14.32 | 23.4 |
| 2023 | 10,095,841 | 937,126 | 1,208,206 | 9.28 | 11.97 | 22.6 |
月足チャート